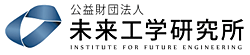社会保障負担の世代間不均衡が招いた「失われた20年」?
生涯のうちに社会保障に対してどのくらいを負担して、どのくらい受益を得るかを世代別(生年別)に算出する世代会計という考え方があります。カリフォルニア大学バークレー校のアラン・J・オーアーバック教授の試算によると、日本は教授が試算対象とした17ヵ国中、世代不均衡が最も大きく、ジュニア世代がシニア世代に比べて2.69倍(169%)の負担となっています。米国の1.51倍(51%)、ドイツの1.92倍(92%)、フランスの1.47倍(47%)、ほぼ完全均衡をとっているカナダ(0%)、ニュージーランド(0%)、逆に高齢者の方が若年層よりも負担の大きいスウェーデン-1.22(-22%)倍などと比べて、日本は若者世代に負担の大きな社会ということになります。
この世代会計の不均衡は、若年層に偏重した社会保障負担によって可処分所得を圧迫し、また、本来個人消費のけん引役である若年層に将来不安による消費性向低下をもたらして、経済成長の阻害要因となり得ます。実際に、上のグラフからわかるように、世代間格差の大きい国ほど、一人当たりGDP成長率が低く抑えられる傾向にあります(相関係数:-0.72)。
上のグラフ上で、スウェーデンは最も世代間の社会保障負担不均衡拡大の問題に直面しましたが、1994年与野党が年金改革に合意後、1990年代後半には力強い経済成長を取り戻し、世代間不均衡も解消され、出生率も向上しています。興味深いのは、スウェーデンの経済回復が、年金制度改革施行後の1999年からでなく、与野党が年金改革に合意した1994年直後から起こっていることです。このことは、世代間不均衡是正の経済的影響において、若年世代の社会保障負担減による実体経済的効果よりも、若年世代の将来不安が払拭されることの心理的効果の方が大きいことを示唆するものです。このグラフは計量経済学的実証を意図したものではありませんが、スウェーデンの経験とは対照的に、バブル崩壊後、世代間の社会保障負担不均衡を放置し低成長の道を歩んだ日本の「失われた20年」の複合要因のうちの重要な一面を説明できていると考えられます。
このような世代間不均衡を緩和するひとつの方策して、私達は子供をもちたいと願うお母さんたちを支援するための「未来世代基金」の設立を社会に提案しています。未来世代基金の詳細はこちら
- センターとプログラム
- 経営と政策
- 経営と行政の課題
- 農林・水産
- 政策調査分析センター
- 政策・施策
- 食品
- 社会課題調査分析センター
- プログラム
- 生活・消費
- 情報通信研究センター
- プロジェクト
- 震災特別企画プログラム
- 課題
- 教育・人材育成
- 政策評価相互研修会
- 産学連携・スタートアップス
- 文化・芸術・宗教
- 旧政策科学研究所
- 科学・技術
- 21世紀フォーラム
- 研究・開発
- 金融・経済
- 国際関係・外交
- イノベーション
- 産業・貿易
- 防衛・安全保障
- 資源・エネルギー
- 行為者と対象者
- 制度・法令
- 規制
- 環境
- 国と地域
- 個人
- 参加
- ネットワーク
- 情報・通信
- 日本
- 組織
- 方法・ソフト・システム
- サービス
- 韓国
- 企業
- 資料・データ・事例
- 中国
- 非営利組織・公企業
- 調査・統計
- 医療・医薬
- 東南アジア
- 教育機関
- 構造
- 介護・福祉
- インド南アジア
- 行政組織・行政関係機関
- 動態・変遷
- 労働
- オセアニア
- 立法機関
- シミュレーション・実験
- 中東
- 司法組織
- 分析・メトリックス
- 宇宙・航空
- ロシア・旧ソ連邦
- 中央
- フォーサイト・予測
- 運輸・交通
- 中欧
- 地方
- 評価
- 観光・レジャー
- 欧州
- 社会・コミュニティ
- 戦略
- 建設・土木・国土
- 北米
- 国家
- マネジメント
- 都市
- 中南米
- 地域
- 農村・漁村・山村
- アフリカ
- グローバル・世界
- 概念・思考・思想・哲学
- 住居・建築
- 防災
- 社会インフラ
- その他